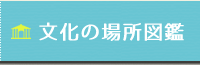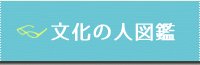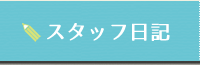2017年10月26日
10月22日に「紙の刀を作ろう」ワークショップを開催しました
10月22日、まさかの台風という悪天候の中でしたが、紙の刀を作ろうワークショップを行いました。今年、ふじのくに子ども芸術大学の講座として3回行いましたが、今回がラスト3回目の開催となりました。悪天候にもかかわらず、24名の方にご参加いただきましてありがとうございました!
講座とワークショップの様子を写真でお伝えします。
最初は「日本刀って何?」の質問から始まりました。
毎回思いますが、刀ワークショップに参加してくれる子ども達は、とにかく歴史好きが多いんです。
歴史的背景も含めた刀の話もすごく熱心に聞いてくれますし、問題を出しても一生懸命色んな答えが出てきます。

では本物の日本刀を見てみましょう。

これだけの近さで本物を見る機会はなかなかないですよね。子ども達の目はすごく真剣です。

柄(つか)を外し、鍔(つば)や刃の構造をみていきます。

一つ一つの部分がもつ意味や役割を解説しました。

分解したものを元に戻したら工作の始まりです。
鞘に巻く布に、型染めで模様をつけていきます。
紋の意味も解説して、7種類の紋から選んで型染めしました。

鍔の片面はオリジナルで考えます。カラフルな鍔が出来ましたよ。

型染めした布を乾かしたら、鞘(さや)の制作です。

ボンドをたっぷり塗って、紙筒に巻き付けていきます。


次は職人気分を味わう柄巻き。丁寧に丁寧に、間があかないように紙紐を巻き付けていきます。これをちゃんとやると、握りやすい刀になりますよ!

刃になる紙筒にアルミを巻いて、はばきになるテープを巻けば、できあがり!

最後にちゃんと鞘に刀が収まるかチェックしたら完成!
力作がたくさん出来たのでご覧ください。





佐野美術館に展示してある本物の刀も見ながら解説をして、今まで以上に刀のことに興味をもってもらえたようです。みんなで記念撮影してワークショップ終了。

今回が佐野美術館に来るのが初めてだよ、という子ども達がたくさんいました。
こんな機会をきっかけに、美術館に行ってみようと思ってくれる子どもが増えてくれたら嬉しいです。
ご協力いただきました佐野美術館様、ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
講座とワークショップの様子を写真でお伝えします。
最初は「日本刀って何?」の質問から始まりました。
毎回思いますが、刀ワークショップに参加してくれる子ども達は、とにかく歴史好きが多いんです。
歴史的背景も含めた刀の話もすごく熱心に聞いてくれますし、問題を出しても一生懸命色んな答えが出てきます。

では本物の日本刀を見てみましょう。

これだけの近さで本物を見る機会はなかなかないですよね。子ども達の目はすごく真剣です。

柄(つか)を外し、鍔(つば)や刃の構造をみていきます。

一つ一つの部分がもつ意味や役割を解説しました。

分解したものを元に戻したら工作の始まりです。
鞘に巻く布に、型染めで模様をつけていきます。
紋の意味も解説して、7種類の紋から選んで型染めしました。

鍔の片面はオリジナルで考えます。カラフルな鍔が出来ましたよ。

型染めした布を乾かしたら、鞘(さや)の制作です。

ボンドをたっぷり塗って、紙筒に巻き付けていきます。


次は職人気分を味わう柄巻き。丁寧に丁寧に、間があかないように紙紐を巻き付けていきます。これをちゃんとやると、握りやすい刀になりますよ!

刃になる紙筒にアルミを巻いて、はばきになるテープを巻けば、できあがり!

最後にちゃんと鞘に刀が収まるかチェックしたら完成!
力作がたくさん出来たのでご覧ください。





佐野美術館に展示してある本物の刀も見ながら解説をして、今まで以上に刀のことに興味をもってもらえたようです。みんなで記念撮影してワークショップ終了。

今回が佐野美術館に来るのが初めてだよ、という子ども達がたくさんいました。
こんな機会をきっかけに、美術館に行ってみようと思ってくれる子どもが増えてくれたら嬉しいです。
ご協力いただきました佐野美術館様、ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。